- 相続手続きで銀行の残高証明書はどんな時に必要なの?
- 残高証明書の取得に必要な書類と手順を知りたい
- 相続した預金や有価証券の手続きの流れを知りたい
- 銀行ごとの相続手続きの違いや注意点を把握したい
相続が発生すると、被相続人が所有していた銀行預金や有価証券の名義変更や換金などの手続きが必要になります。その最初のステップとなるのが「残高証明書」の取得です。
この記事では、相続手続きに必要な銀行残高証明書の取得方法と必要書類について、実務経験豊富な公認会計士試験合格者の視点から解説します。この記事を読めば、相続手続きの第一歩をスムーズに進められるようになります。
 ぜいむたん
ぜいむたん


1. 銀行残高証明書の基礎知識と重要性
銀行残高証明書とは、被相続人の死亡時点における預金残高を証明する書類です。相続手続きの初期段階で取得することで、相続財産の把握と相続税申告の基礎資料となります。
残高証明書が必要となる4つのケース
- 相続税申告で預金の既経過利息を計算する必要がある場合
- 被相続人が有価証券(株式・投資信託など)を所有していた場合
- 遺産分割協議の資料として相続財産を正確に把握する必要がある場合
- 複数の相続人で財産を公平に分配するための基礎資料として
普通預金のみで通帳により相続開始時の残高が明確にわかる場合は、必ずしも残高証明書は必要ありません。ただし、相続税申告を行う場合は、念のため残高証明書を取得しておくと安心です。



相続手続きをスムーズに進めるためには、被相続人の全ての預金口座と金融資産を把握することが重要です。残高証明書は、その金融資産の全体像を明確にするための第一歩となります。
2. 残高証明書の取得手順と必要書類
残高証明書の取得は、金融機関によって手順や必要書類が異なります。しかし、基本的な流れは共通しています。まずは各銀行に問い合わせて具体的な手続き方法を確認しましょう。
残高証明書請求書類の入手方法
- 銀行の窓口で直接受け取る
- 銀行に電話して郵送してもらう
- 銀行のウェブサイトからダウンロードする(一部の銀行のみ)






| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 残高証明書発行依頼書 | 経過利息計算発行依頼書を含む |
| 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本 | 法定相続情報一覧図で代用可 |
| 代表相続人と被相続人の関係がわかる戸籍 | および代表相続人の現在戸籍 |
| 代表相続人の印鑑証明書 | 有効期限内のもの(通常6ヶ月以内) |
| 代表相続人からの委任状 | または業務契約書(代理人が手続きする場合) |
| 代理人の会社の印鑑証明書・全部事項証明書 | 代理人が法人の場合 |
| 手続き人の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
印鑑証明書の有効期限は銀行によって異なります。多くの銀行では6ヶ月以内のものが必要ですが、中には3ヶ月以内のものを求める金融機関もあります。事前に電話で確認しておくことをおすすめします。また、代理人(税理士など)に依頼する場合は、相続人全員分の委任状と印鑑証明書が必要になるケースがほとんどです。



銀行への確認事項チェックリスト
- 定期預金の既経過利息の記載は可能か、必要書類は別途あるか
- 印鑑証明書や各種証明書類の有効期限は何ヶ月か
- 委任状の有効期限はあるか
- 委任状の形式は任意でよいか
- 窓口提出の場合、予約は必要か
- 証明書の発送先を事務所など別住所にすることは可能か
- 手数料はいくらで、支払方法はどのようになっているか
残高証明書の取得から実際の相続手続きまでは、一連の流れとして進めることが効率的です。次に、実際の相続手続きについて見ていきましょう。
3. 銀行預金の相続手続き完全ガイド
残高証明書を取得した後は、実際の相続手続きに進みます。銀行預金の場合、名義変更または解約して引き出す手続きが必要です。ここでは、具体的な手順を解説します。
残高証明書を取得する際に一緒に依頼するか、最寄りの支店で取得します。各銀行によって様式が異なるため、必ず該当銀行の専用用紙を入手しましょう。
相続手続きには、戸籍謄本や印鑑証明書など多くの書類が必要です。特に相続人が複数いる場合は、全員分の書類を準備する必要があるため、早めの準備が重要です。
必要書類を提出し、相続手続きを行います。窓口が混雑している場合があるため、可能であれば事前予約をしておくとスムーズです。
手続き完了後、指定口座に振り込まれます。一般的に、手続きから入金までには数日〜1週間程度かかります。
銀行預金相続手続きに必要な書類
- 相続手続き依頼書
- 被相続人の出生~死亡までの連続戸籍、相続人全員の現在戸籍(法定相続情報一覧図で代用可)
- 相続人全員の印鑑証明書(有効期限内のもの)
- 相続人全員の委任状または業務契約書(代理人が手続きする場合)
- 遺産分割協議書/遺言書/検認済証明書/相続放棄受理申述書(該当する場合)
- 被相続人の通帳(あればカード)
- 振込先口座情報(解約金の受取口座)






銀行預金だけでなく、被相続人が有価証券(株式や投資信託)を所有していた場合は、別途手続きが必要になります。次のセクションでは、有価証券の相続手続きについて解説します。
4. 有価証券の相続手続き~3つのパターン~
被相続人が有価証券(株式や投資信託)を所有していた場合は、銀行預金とは異なる手続きが必要です。有価証券の相続手続きには、大きく分けて3つのパターンがあります。
1. 換価換金して相続人預金口座に振り込むパターン
有価証券を売却して現金化し、相続人の預金口座に振り込む方法です。主に銀行での手続きに多いパターンです。
- 「被相続人〇〇代表口座△△」という換価換金のためだけの口座を開設
- 相続人の手間が少なく済む方法
- 相続税申告の際に取得価額の証明が必要
- 市場価格の変動リスクがある点に注意
2. 株式や投資信託のまま相続人証券口座に移管するパターン
証券会社での手続きに多いパターンで、さらに2つのケースに分かれます。
- 手続きが比較的簡単
- 基本的には相続人の証券口座番号を記入するだけ
- 必要書類:〇〇口座開設者死亡届出書、移管依頼書
3. 特別口座に預けられている株式の相続手続き
「特別口座」とは、2009年の株券電子化以前に紙の株券を所有していて、証券口座に預けなかった場合に、信託銀行に開設される口座です。このケースでは以下の手続きが必要です。
信託銀行に相続手続きを依頼します。
株式が相続人の特別口座に振り替えられます。
特別口座から相続人の証券口座に株式を移管します。
未受領配当金がある場合は、振込先預金口座を共同相続人同意書に記入します。
特別口座では株式の売買ができません。相続後に売却したい場合は、必ず証券口座への振替が必要です。また、特別口座の管理会社は株式の発行会社によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。



5. 金融機関別の相続手続きの違い
相続手続きは金融機関によって細かな違いがあります。特にゆうちょ銀行は、一般の銀行とは異なる特徴があるため、注意が必要です。
| 項目 | ゆうちょ銀行 | 一般の銀行 |
|---|---|---|
| 解約金の振込先 | 原則ゆうちょ銀行口座のみ | 他行口座への振込可能 |
| 委任状の有効期限 | 一部支店では設定あり | 基本的になし |
| 残高証明書 | オンライン発行サービスあり | 窓口申請が基本 |
| 手続き所要時間 | 比較的短い(1~2週間) | 銀行により異なる |
| 本人確認書類 | 通常必要 | 通常必要 |






証券会社の特徴と注意点
証券会社での相続手続きでは、以下の点に注意が必要です:
- ネット証券と対面型証券会社で手続き方法が異なる
- 複数の証券会社に口座がある場合、それぞれで手続きが必要
- 特定口座の取得価額の引継ぎができる場合と、できない場合がある
- 相続税申告のために取得価額の証明書を入手しておくことが重要
freeeの相続株式に関する記事も参考になります。
地方銀行の特徴と注意点
地方銀行での相続手続きでは、以下の点に注意が必要です:
- 支店が少ないため、遠方の場合は郵送対応を確認する
- 書類の有効期限が都市銀行より短い場合がある
- 独自の様式を使用している場合が多い
- 予約制を導入している支店も増えているため事前確認が必要
6. 相続手続きを効率的に進めるための実務ポイント
相続手続きは複数の金融機関との対応が必要になることが多く、書類の管理と進捗管理が重要です。ここでは、実務上のポイントを紹介します。
書類管理の方法
- 金融機関ごとにフォルダを作成し、提出書類や受領書類を整理する
- 相続手続き管理表を作成し、各銀行の進捗状況を一覧で確認できるようにする
- 書類のコピーを取っておき、原本は別途保管する
- 提出済みの書類と未提出の書類を明確に区別する
- 書類不備があった場合の対応記録も残しておく
金融機関に問い合わせる前の確認事項
- 印鑑証明書の期限(金融機関によって異なる)
- 既経過利息記載の依頼書は別にあるか
- 遠方の地方銀行の場合、郵送での手続きは可能か
- 窓口来店の際、事前予約は必要か
- 在職証明書、使用人への委任状は必要か
- 手数料はいくらで、支払方法はどうなっているか
- オンラインバンキングのID・パスワードがある場合の手続き方法
金融機関に問い合わせる前に、お客様(相続人)に口座を凍結してよいか必ず確認しておきましょう。相続手続きを開始すると口座が凍結されるため、日常的に使用している口座の場合は注意が必要です。
金融機関によっては、相続手続き中に他の取引(振込や引き出し)ができなくなることがあります。特に生活費の引き出しなどに使用している口座の場合は、手続きのタイミングを慎重に検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
- 残高証明書の発行にはどのくらいの日数がかかりますか?
-
銀行によって異なりますが、都市銀行の場合は1週間程度、地方銀行や信用金庫の場合は2週間程度かかることが一般的です。ただし、繁忙期や書類不備があると、さらに時間がかかる場合があります。また、手続きの混雑状況によっても変わりますので、余裕をもって申請することをおすすめします。
- 相続人が多数いる場合、全員の書類が必要になりますか?
-
原則として、相続手続きには相続人全員の書類(印鑑証明書や委任状など)が必要です。ただし、残高証明書の取得だけであれば、代表相続人のみの書類で対応できる銀行もあります。相続手続きの段階では、基本的に相続人全員の書類が必要になります。全員分の書類を集めるのに時間がかかることがあるため、早めの準備が重要です。
- 通帳やキャッシュカードを紛失した場合でも手続きはできますか?
-
通帳やキャッシュカードを紛失した場合でも、基本的には手続きは可能です。ただし、本人確認や相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)がより重要になります。銀行によっては追加の確認書類を求められる場合もあります。また、紛失届の提出が必要となる場合もありますので、事前に銀行に相談することをおすすめします。
- 相続税の申告が必要ない場合でも残高証明書は必要ですか?
-
相続税の申告が不要な場合でも、銀行での相続手続きには残高証明書が必要になることがあります。特に複数の相続人がいる場合の遺産分割協議の資料として、また相続財産を正確に把握するためにも残高証明書は有用です。相続発生時点での正確な残高を証明する公式書類として、トラブル防止のためにも取得しておくことをおすすめします。
- 預金の残高証明書と残高計算書の違いは何ですか?
-
残高証明書は、ある時点(相続の場合は被相続人の死亡時点)での預金残高を証明する公式書類です。一方、残高計算書(または残高算出表)は、定期預金などの既経過利息を含めた詳細な計算内容を示す書類です。相続税申告では、両方の書類が必要になることが多いです。特に定期預金がある場合は、既経過利息の計算のために残高計算書も一緒に申請することをおすすめします。
まとめ:相続手続きを確実に進めるためのポイント
必要書類のリストアップと各銀行の要件確認を行いましょう。特に印鑑証明書の有効期限や委任状の形式など、銀行ごとに異なる要件を事前に把握しておくことが重要です。
相続財産の正確な把握のため、まずは残高証明書を取得しましょう。定期預金がある場合は、既経過利息の記載も忘れずに依頼しましょう。
銀行預金と有価証券それぞれの手続きを適切に行いましょう。金融機関ごとの違いに注意し、必要書類を過不足なく準備することが大切です。
複数の金融機関との手続きを効率的に管理しましょう。相続手続き管理表を作成し、各金融機関の進捗状況を一元管理することで、漏れやミスを防ぐことができます。
相続手続きは複雑で時間がかかることもありますが、適切な準備と手順を踏むことで、スムーズに進めることができます。専門家のサポートを受けながら、一つひとつ確実に手続きを進めていきましょう。



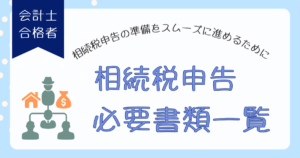
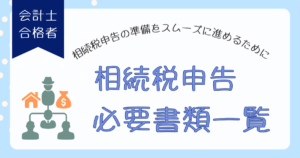

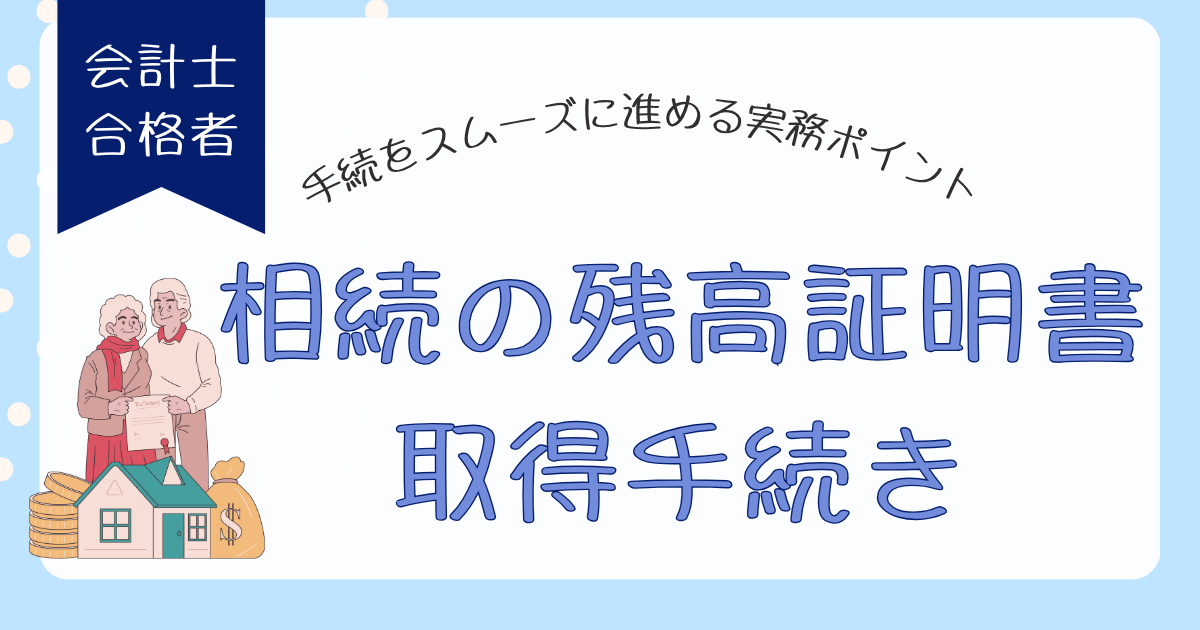
コメント