- 会社設立時に税務署へ提出すべき書類が分からない
- 提出書類の期限や優先順位が知りたい
- 適格請求書発行事業者(インボイス)の登録申請方法を知りたい
- 書類提出の漏れがないか確認したい
法人設立後は、様々な税務関係の書類を提出する必要があります。提出先は税務署だけでなく、都道府県や市区町村の役所なども含まれます。期限内に適切な書類を提出しないと、後々トラブルになる可能性もあるため注意が必要です。国税庁のガイドラインに従って正確に手続きを行いましょう。
この記事では、法人設立時に税務署へ提出する必要がある必要書類の一覧と、2023年10月から始まったインボイス制度に関する適格請求書発行事業者登録申請について解説します。税務手続きをスムーズに進めるためのポイントも紹介していきます。
 ぜいむたん
ぜいむたん


税務署へ提出する主な書類一覧
会社設立時に税務署へ提出する主な書類は以下の5つです。それぞれ必要性や提出期限が異なるため、しっかり確認しておきましょう。
提出すべき主な書類
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 申告書の提出期限の延長の特例の申請書
- 適格請求書発行事業者登録申請書
法人設立届出書
必ず提出が必要な基本書類です。会社名、所在地、代表者名、事業内容、資本金額などの基本情報を記載します。






添付書類と提出期限
※2019年4月以降、国税庁への提出分は定款のみの添付で良くなりましたが、都道府県や市町村への提出時は定款を付けておいた方が無難です。
青色申告の承認申請書
青色申告は、欠損金の繰越控除や各種特別控除などの税制上のメリットがある申告方式です。
- 欠損金の繰越控除(最長10年間):赤字を10年間繰り越せる
- 少額資産の一括費用計上:30万円未満の資産を一時の費用にできる。






青色申告の期限と条件
給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇用し給与を支払う予定がある場合に提出する書類です。基本的には設立時にまとめて提出することが多いです。
給与支払関係の届出






源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員に給与を支払っている会社や個人事業主は、給与から源泉所得税を天引きして、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。
でも、毎月の納付って正直面倒ですよね。そんなときに使えるのが「納期の特例」という制度です。
納期の特例のメリット
この特例を申請すると、源泉所得税の納付は年2回にまとめてOKになります。
- 1月~6月分 → 7月10日までに納付
- 7月~12月分 → 翌年1月20日までに納付
つまり、毎月の納付が不要になり、事務作業の負担が軽くなります。
さらに、納税のタイミングが後ろ倒しになるので、資金繰りの改善にもつながります。
申告書の提出期限の延長の特例の申請書
決算後の税務申告書の提出期限を延長するための申請書です。決算書類の作成に時間がかかる企業にとって有用です。
提出は義務ではありませんが、提出しておくと1か月遅れてもよいので、何かあった場合の保険になります。








法人設立届出に関する3つの重要ポイント
設立届出を提出する際に気をつけるべきポイントを解説します。
1. 提出先について
税務関係の書類は、税務署だけでなく地方自治体にも提出が必要です。
- 国税関係:所轄の税務署
- 地方税関係:都道府県税事務所と市区町村役場
地方自治体への提出書類は国税庁への提出書類と様式は似ていますが、通常は登記事項証明書のコピーなど追加の添付書類が必要となります。
2. 提出方法と期限
書類提出は以下の3つの方法から選べます。
- 税務署の窓口に直接提出
- 郵送による提出
- e-Taxシステムを通じた電子提出
各書類にはそれぞれ提出期限があります。特に法人設立届出書は会社登記から2ヶ月以内という明確な期限があるため、注意が必要です。






3. 書類の優先順位
すべての書類を同時に提出する必要はありませんが、以下の優先順位で対応することをおすすめします。
- 法人設立届出書(登記後2ヶ月以内)
- 青色申告の承認申請書(設立3ヶ月以内等)
- 給与関係の届出書(給与支払開始前)
- その他の申請書



法人設立届出は以下でも解説しているから参考にしてや
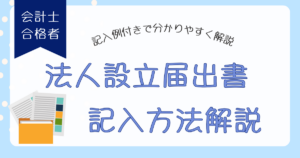
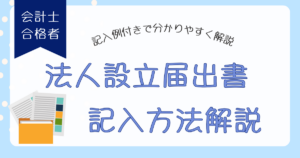
適格請求書発行事業者登録申請について
2023年10月1日から導入された消費税のインボイス制度に関連する「適格請求書発行事業者登録申請書」についても理解しておく必要があります。






登録の条件と申請方法
適格請求書発行事業者として登録できるのは消費税の課税事業者のみです。申請書は税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
申請方法:
- 税務署の窓口に直接提出
- 郵送(管轄のインボイス登録センターへ)
- e-Taxシステムを通じた電子申請
新設法人の特例
新設法人が事業開始日から登録を受けるための特例があります。
- 事業開始日の属する課税期間の末日までに登録申請書を提出
- 申請書に「課税期間の初日から登録を受けたい」旨を記載
これにより、課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
また、2023年10月1日から2029年9月30日までの期間中に登録申請する場合は、特例として登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合、別途「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。






- 取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けられるため、取引上有利になる
- 事業者としての信頼性が向上する
- B2B取引が多い場合、取引先から選ばれやすくなる
小規模事業者向け負担軽減措置(2割特例)
インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者となった小規模事業者向けに、2026年(令和8年)までの申告分について、売上税額の8割を差し引いて納税額を計算できる「2割特例」が設けられています。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
- 免税事業者から適格請求書発行事業者となったこと
- 簡易課税制度を選択していないこと
法人設立時の書類提出チェックリスト
法人設立時の書類提出を漏れなく行うためのチェックリストです。
提出書類チェックリスト
- 法人設立届出書(登記後2ヶ月以内)
- 青色申告の承認申請書(設立3ヶ月以内等)
- 給与支払事務所等の開設届出書(給与支払開始前)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(必要に応じて)
- 申告書の提出期限の延長の特例の申請書(必要に応じて)
- 地方自治体への設立届出書(都道府県・市区町村)
- 適格請求書発行事業者登録申請書(希望する場合)
- 法人設立届出書は法務局の登記だけでは足りないのですか?
-
法務局での会社登記と税務署への法人設立届出書の提出は別物です。登記だけでは税務署に会社の存在が通知されないため、必ず別途法人設立届出書を提出する必要があります。登記後2ヶ月以内という期限も忘れないようにしましょう。
- 青色申告の承認申請書を提出し忘れるとどうなりますか?
-
青色申告の承認申請書を期限内に提出しなかった場合、最初の事業年度は青色申告ができず、白色申告となります。その場合、欠損金の繰越控除などの税制上のメリットを受けることができません。実務上、ほとんどの法人が青色申告を選択しています。
- 適格請求書発行事業者の登録は必須ですか?
-
適格請求書発行事業者の登録は必須ではありませんが、取引先が課税事業者で仕入税額控除を受けたい場合には、取引先から登録を求められる可能性があります。BtoB取引が中心の場合は特に登録を検討した方がよいでしょう。事業形態や顧客層に応じて判断する必要があります。
- e-Taxで電子申請するメリットはありますか?
-
e-Taxでの電子申請には、24時間いつでも提出できる、窓口に行く手間が省ける、書類の保管が電子的に行える、といったメリットがあります。また、一度設定すれば、その後の手続きもスムーズに行えるので、長期的に見ると効率的です。
まとめ:法人設立時の税務手続きと適格請求書発行事業者登録のポイント
会社登記から2ヶ月以内に提出するため、最優先で対応する
税務上のメリットが大きいため、特に理由がなければ申請しておく
従業員や役員に報酬を支払う場合に必要な手続きを行う
取引先や事業形態に合わせて登録の判断をする
法人設立時の税務署への書類提出は、会社経営の基盤となる重要な手続きです。期限を守り、必要な書類を漏れなく提出することで、スムーズに事業をスタートさせることができます。
また、インボイス制度への対応として適格請求書発行事業者としての登録を検討する場合は、事業モデルや顧客層、財務状況などを考慮して登録のタイミングを慎重に判断することが重要です。クラウド会計ソフトなどのサービスを活用すると、適格請求書の発行や管理も効率化できます。
会社設立後の税務手続きは一見複雑ですが、このチェックリストを参考にすれば漏れなく対応できるはずです。



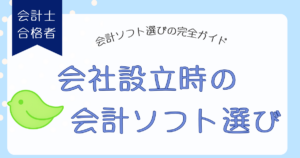
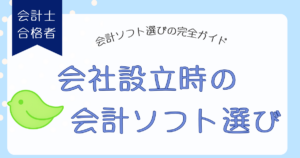

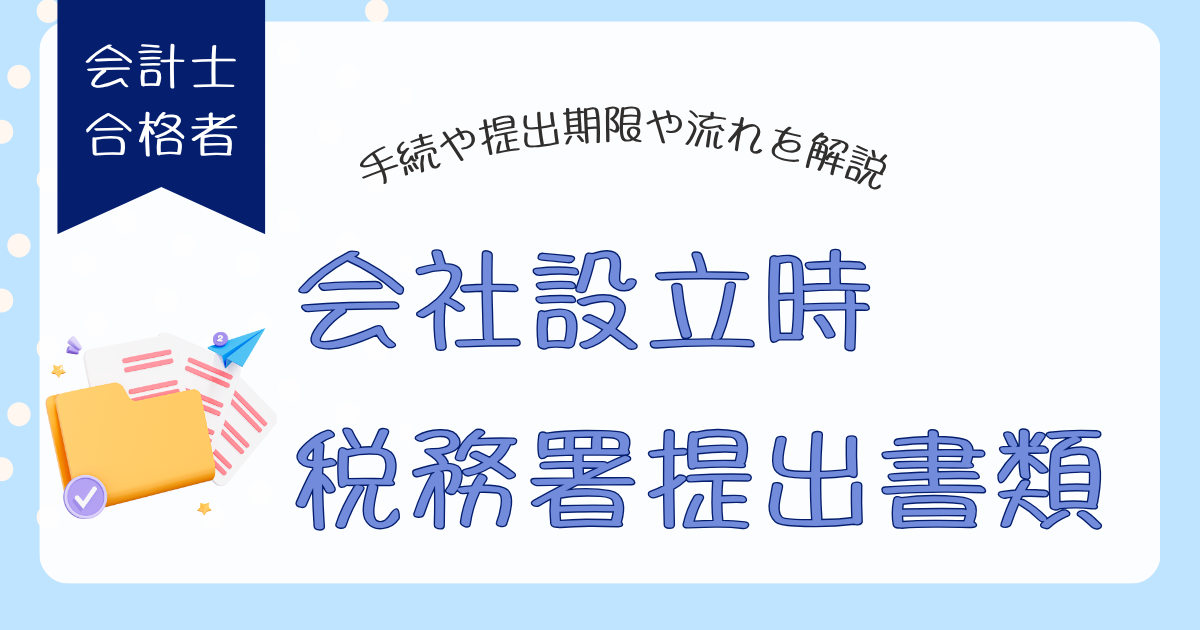
コメント