この記事では、不動産所得と事業所得の両方を持つ個人事業主の方に向けて、確定申告の正しい方法や注意点について解説します。複数の所得源がある場合の記帳方法や青色申告のメリット、損益通算のポイントなど、実務に役立つ情報を網羅しています。
- 不動産所得と事業所得の両方がある場合、青色申告はどのように行えばいいの?
- 不動産所得の赤字を事業所得と損益通算できる条件は?
- 両方の所得がある場合の記帳・会計処理で気をつけるべきことは?
不動産所得と事業所得の基本と重要ポイント
「不動産所得」と「事業所得」の違い
- 不動産所得:土地・建物等の賃貸による収入を対象とし、原則として不労所得型と位置付けられます。
- 事業所得:自らの労働や資本を投下して継続的に営む事業活動(フリーランス等)から得られる所得を指します。
両方の所得がある場合、それぞれを明確に区分して記帳・集計・申告することが求められます。収入と経費の記録は所得の種類ごとに分けて管理する必要がありますが、資産や負債の状況を示す貸借対照表については合算して作成するのが一般的です。
 イザーク
イザーク所得区分によって、青色申告の特別控除(最大65万円)を受けられるかどうかも変わってきますので、自分の状況を正確に把握しておきましょう。
不動産所得と事業所得の計算方法
所得税の計算と損益通算のポイント
- 所得税は総合課税方式で、すべての所得を合算して累進税率が適用されます。
- 不動産所得の赤字を事業所得の黒字と通算して税負担を軽減できる場合があります。
- ただし、土地取得に伴う借入金の利子などは通算対象外となる点に注意が必要です。
- また、家族に対する過大な専従者給与や形式的な外注費、譲渡所得や一時所得との通算も不可である点に注意が必要です。
・不動産所得:家賃収入300万円、経費250万円 → 黒字50万円
・事業所得:売上600万円、経費400万円 → 黒字200万円
→ 不動産所得から青色申告特別控除65万円のうち50万円を控除
→ 残りの15万円を事業所得から控除
→ 課税対象所得:185万円(250万-65万)
損益通算できない不動産所得の赤字がある場合の対策
- 青色申告による繰越期間:青色申告を行っている場合、純損失(赤字)を最長3年間繰り越すことができます。例えば、2025年に生じた純損失は、2026年から2028年までの各年分の所得から控除することが可能です。
- 繰越対象外となるケース:生活費が混入していた場合や、事業実態がないと判断された場合などは、繰越控除の対象外となる可能性があります。適切な記帳と事業実態の証明が重要です。



不動産所得と事業所得「両方ある場合」の記帳・会計処理のポイント
記帳・会計処理でよくあるミスと対策
- 共通費用の按分:車両費、通信費、事務所家賃など両方の所得に関わる共通費用は、合理的な基準(使用割合、売上比率など)で按分して記帳する必要があります。
- 固定資産台帳の管理:減価償却資産が両方の所得にまたがる場合でも、固定資産台帳自体は分けずに一元管理するのが原則です。ただし、使用区分は明確にしておきましょう。
- 所得区分の誤り:家賃収入を誤って事業所得に含めて記帳するなどの所得区分の誤りは、税務調査で否認される可能性が高いので注意が必要です。



申告・納付の手続き
確定申告の方法と期限
不動産所得と事業所得の両方がある場合の確定申告手続きは、以下の手順で進めましょう。
不動産所得と事業所得は、それぞれ独立した収支計算が必要です。
「不動産所得用」と「一般用(事業所得用)」の2種類を別々に作成します。これは国税庁の要件で、兼業の場合は必ず両方を提出する必要があります。
所得税は合算して課税される(総合課税)ため、申告書に両方の所得を記載します。
不動産所得が赤字であれば、事業所得と通算して税額軽減が可能かどうか確認します。
確定申告の期限は原則として翌年3月15日です。青色申告特別控除や各種特例を適用するには期限内の申告が必須となります。
必要書類と証憑の準備
| 区分 | 必要書類・証憑 |
|---|---|
| 不動産所得関連 | 賃貸契約書、家賃入金明細、固定資産税通知書、管理費支払証憑など |
| 事業所得関連 | 請求書、領収書、仕入台帳、通帳の入出金記録など |
| 共通書類(青色申告用) | 総勘定元帳、仕訳帳、帳簿類(電子帳簿保存も可) |
節税対策と活用できる特例
不動産所得と事業所得に関する控除・特例制度の活用法
- 不動産所得・事業所得の両方に適用可能な控除として、青色申告特別控除・専従者給与・減価償却費などがあります。
- 不動産所得特有:固定資産税や借入金利子の必要経費化。
- 事業所得特有:事業用車両や通信費等の経費計上。



よくある質問
- 不動産所得と事業所得の両方で合計130万円(65万円×2)の青色申告特別控除は受けられますか?
-
いいえ、青色申告特別控除の上限は合計で65万円(条件により55万円または10万円)までです。不動産所得と事業所得の両方があっても、控除額は合計で最大65万円です。控除の適用順序は、まず不動産所得から控除し、控除しきれない残額を事業所得から控除します。
- 不動産所得の赤字を給与所得と損益通算できますか?
-
不動産所得の赤字は、事業所得などの他の所得と損益通算できますが、給与所得とは原則として損益通算できません。ただし、土地等の取得に係る借入金の利子による赤字は、他の所得との損益通算もできない点に注意が必要です。
- 不動産所得と事業所得の決算書の作成方法について教えてください。
-
不動産所得と事業所得の両方がある場合(兼業の場合)は、「不動産所得用」と「一般用(事業所得用)」の2種類の決算書を別々に作成する必要があります。これは国税庁の要件で、どちらか一方だけでは不十分です。日々の帳簿記録(仕訳帳・総勘定元帳など)は所得の種類ごとに区分して記帳することが強く推奨されます。青色申告決算書の「損益計算書」はそれぞれの所得ごとに作成しますが、「貸借対照表」は両方の所得を合算して1つにまとめて作成します。
専門家のアドバイス
よくある間違いや注意点
- 不動産所得と事業所得を混同して記帳 : それぞれ帳簿・決算書を分ける必要があります。混在させると税務調査で否認されるリスクがあります。
- 不動産所得の赤字が通算できないケース:土地取得のための借入利子は不動産所得の赤字とすら通算できません。また、家族への過大な専従者給与や形式的な外注費も損益通算が否認されるケースがあります。
- 譲渡所得や一時所得との通算は不可:不動産所得の赤字は、事業所得・給与所得など一部の所得とのみ通算可能で、譲渡所得や一時所得との通算はできません。
- 青色申告65万円控除が受けられないケース:電子申告・複式簿記などの要件を満たさないと、55万円または10万円控除に減額されるケースがあります。
さらに重要なポイントとして、事業所得が「赤字」、不動産所得が「黒字」の場合でも、不動産所得が業務的規模(事業的規模でない場合)であっても、青色申告特別控除の最大65万円の適用を受けることができます。これは、「事業所得を生ずべき事業を営む者」に該当するためです。ただし、事業所得について複式簿記による帳簿を作成し、貸借対照表を添付していることが条件となります。
関連情報リンク
まとめ:不動産所得と事業所得について押さえておくべきポイント
不動産所得用と一般用(事業所得用)の両方を作成・提出する必要があります。兼業の場合は、片方だけでは不十分です。
両方の所得があっても、控除の合計上限は65万円です。控除順序は不動産所得から先に適用します。
不動産所得の赤字と事業所得の黒字を損益通算することで、総合課税の対象となる所得金額を減らせます。ただし、土地等の取得に係る借入金の利子による赤字は損益通算できません。
青色申告の場合、損益通算できない赤字でも、最長3年間繰り越して将来の所得から控除できる可能性があります。
共通費用(車両費、通信費など)は、合理的な基準で按分して記帳する必要があります。恣意的な按分は税務調査で否認されるリスクがあります。
正確な申告で、適切な節税と税務リスクの回避を両立させましょう。



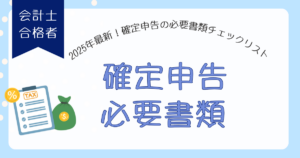
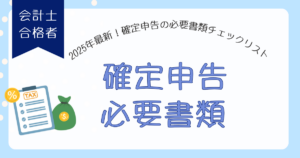


コメント